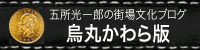この季節のお奨めコラム
お釈迦さんの鼻くそ 花供租あられをご存知だろうか

香ばしく甘辛い味がする。硬くなった鏡餅を細かく切り、黒豆と白豆とに混ぜ、炒った後砂糖醤油を塗(まぶ)した素朴なお菓子である。
どこで聞き覚えたのか、「お釈迦さんの鼻くそや」と… 続きを読む
花灯路の夜話

花灯路の宵の食事となると、東山界隈で予約することになる。
どこへ往けば良いか、いいころを紹介してほしいと、よく問われる… 続きを読む
京の仕出し屋 その二
来客予定の持て成しに、仕出し屋で懐石膳を注文すると、先付、八寸、造り、吸い物、焼き物、揚げ物、酢の物、蒸し物、ごはん、水物と勢ぞろいする。
来客があった場合、できる限りの腕を振るって温かい料理でもてなすのが礼節であると言えども、京都で心のこもった… 続きを読む
続 秀吉が京都に残したもの 聚楽第

半農半兵の農家に生まれた秀吉は、武将となり天下人となっても、自身の中にコンプレックスがあったのであろうか。
織田家に仕えるまでの経緯については不確かで、秀吉の口承伝記にあっても… 続きを読む
智積院の梅園に佇む
春の穏やかな陽射しの日があり、寒の戻りの日があり、そして東寺の河津桜の開花が報じられた。その頃奈良の東大寺では、二月堂の「お水取り」が行われている。
京都では、東山花灯路に涅槃図公開の声が俄かに聞こえだし、そろそろ本格的な春が近づいてきたなと思う。
… 続きを読む
将軍塚青龍殿建立と国宝青不動

平成26年10月4日の京都東山将軍塚青龍殿落慶をめざした、青蓮院門跡の東伏見慈晃門主の決意はどれ程のものであったのだろうか。… 続きを読む
松尾の葵祭

京都の皐月といえば、上賀茂、下鴨の両神社での葵祭(賀茂祭)である。
斎王代や藤の花の掛かった牛車などの巡行が、都大路から下鴨、上賀茂の両神社へと平安王朝絵巻を繰り広げ、路頭の儀、… 続きを読む
京の仕出し屋 その一
京の街角を歩くと、「料理・仕出し」という看板や暖簾を見かけるだろう。
戦後の核家族化や住宅事情の変化、節句などの歳時記における祝い事や、宗教への接し方が希薄になり、「仕出し」というもの、そのものを利用する機会が減っている。そのため、その機能をどう… 続きを読む
ご利益はぽっくり

給料明細を見るたびに、控除されている厚生年金や介護保険料などの額に驚き嘆いている。
積立金なら取り崩すなり、引き出すなりできるのだが、相互扶助の国民の負担費用であるというから、… 続きを読む
コンテンツ移動のお知らせ
谷口年史 :京都ミステリー紀行 http://kyotocf.com/column/kyo-mystery/
は最新号以降、下記サイトに移転しました。
旧コラムはどちらのサイトでもご覧いただけます。
京都CF! 「京都コラム」http://kyotocf.com/column/